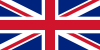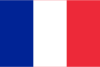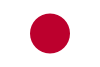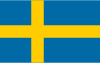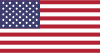温度測定は、接触式と非接触式の 2 つに分類できます。実際には、熱電対と Pt 100 センサーが、前者のグループで最もよく使用されています。これらは測定対象物に接触する必要があり、原則として、対象物と同じ温度を測定します。そのため、応答性が比較的遅くなります。非接触式センサーは、対象物から放射される赤外線(IR)エネルギーを測定し、応答時間が短く、移動している対象物や、真空中にある対象物、その他の理由でアクセスできない対象物の測定によく使用されます。
赤外線温度計やパイロメーターは、研究や産業で広く使われている高度なセンサーだよ。このエッセイでは、この測定原理の基礎となる理論と、潜在的なユーザーが直面するさまざまなアプリケーション固有のパラメータに対処するためにこの理論がどのように役立つかをわかりやすく説明しているよ。
赤外線温度測定の基礎
はじめに

図 1 電磁スペクトル
理論と基礎
赤外線放射は、アイザック・ニュートン卿が1666年に太陽光をプリズムに通し、虹の色に分離したときに発見された。1880年、ウィリアム・ハーシェル卿は、個々の色の相対的なエネルギーを決定することで、次のステップに進んだ。彼はまた、可視スペクトル以外のエネルギーも発見した。1900年代初頭には、プランク、シュテファン、ボルツマン、ウィーン、キルヒホッフが電磁スペクトルの活動をさらに定義し、赤外線エネルギーを記述する定量的データと方程式を確立しました。
赤外線温度計は、絶対零度(0°ケルビン)以上の温度を持つすべての物質や物体から放射される赤外線を測定することで温度を測定します。最も単純な設計では、レンズが赤外線エネルギーを検出器に集光し、検出器がエネルギーを電気信号に変換します。周囲温度を補正した後、この信号を表示することができる。この構成により、測定対象物に触れることなく、一定の距離から温度を測定することができる。このため、赤外線温度計は、熱電対や他のセンサーが使用できない、あるいは不正確な結果をもたらす測定作業に適している。代表的な例としては、動いている物体や非常に小さい物体、生きている部品や腐食性のある化学物質の測定、強い電磁場での測定、真空やその他の密閉された環境での測定、速い応答時間が要求される用途などがあります。
赤外線温度計の最初の設計は19世紀から存在していました。いくつかのコンセプトは、1911年に出版されたチャールズ・A・ダーリングの著書 "Pyrometry "の中で紹介されている。
これらのコンセプトを実用化する技術が利用できるようになるまでには、1930年までかかった。それ以来、これらの測定器は継続的な発展を遂げ、その過程で広範な知識と応用経験が得られてきた。今日、このコンセプトは標準的な測定方法として確立され、産業界や研究機関で使用されている。
赤外線温度計は、絶対零度(0°ケルビン)以上の温度を持つすべての物質や物体から放射される赤外線を測定することで温度を測定します。最も単純な設計では、レンズが赤外線エネルギーを検出器に集光し、検出器がエネルギーを電気信号に変換します。周囲温度を補正した後、この信号を表示することができる。この構成により、測定対象物に触れることなく、一定の距離から温度を測定することができる。このため、赤外線温度計は、熱電対や他のセンサーが使用できない、あるいは不正確な結果をもたらす測定作業に適している。代表的な例としては、動いている物体や非常に小さい物体、生きている部品や腐食性のある化学物質の測定、強い電磁場での測定、真空やその他の密閉された環境での測定、速い応答時間が要求される用途などがあります。
赤外線温度計の最初の設計は19世紀から存在していました。いくつかのコンセプトは、1911年に出版されたチャールズ・A・ダーリングの著書 "Pyrometry "の中で紹介されている。
これらのコンセプトを実用化する技術が利用できるようになるまでには、1930年までかかった。それ以来、これらの測定器は継続的な発展を遂げ、その過程で広範な知識と応用経験が得られてきた。今日、このコンセプトは標準的な測定方法として確立され、産業界や研究機関で使用されている。
測定原理
すでに述べたように、0°K以上の温度を持つすべての物体は赤外線エネルギーを放射する。赤外線は電磁スペクトルのうち、可視光と電波の中間に位置する部分である。赤外線の波長は、図1に示すように0.7µmから1000µmである。しかし実際には、この周波数範囲のうち、温度測定に適しているのは0.7~20μmの波長だけである。波長20μm以上に放出される微量のエネルギーを測定するのに十分な感度を持つ検出器は、現在のところ存在しない。
この曲線(図2)は、700Kから1300Kの温度範囲における黒体から放出されるエネルギーを表している。見てわかるように、そのほとんどは可視光線の範囲を超えています。赤外線放射は人間の目には知覚できませんが、動作原理や応用で生じる問題を理解するためには、この放射を可視光線として考えることが役立ちます。
多くの点で、赤外線放射は実際には可視光線と同じように振る舞います。赤外線放射は、放射源から直線的に遠ざかり、ビーム経路内の物体によって反射または吸収されます。人間の目に透明でないほとんどの物体から、赤外線は部分的に反射し、部分的に吸収される。吸収されたエネルギーの一部は内部で反射され、一部は再び放射される。これは、ガラスや気体、薄い透明プラスチックフィルムなど、人間の目には透明な物体にも当てはまる。さらに、放射線の一部は物体を透過する。図3は、これらの過程を示している。これらの過程を総合して、私たちは物体や物質の放射率と呼んでいる。
この曲線(図2)は、700Kから1300Kの温度範囲における黒体から放出されるエネルギーを表している。見てわかるように、そのほとんどは可視光線の範囲を超えています。赤外線放射は人間の目には知覚できませんが、動作原理や応用で生じる問題を理解するためには、この放射を可視光線として考えることが役立ちます。
多くの点で、赤外線放射は実際には可視光線と同じように振る舞います。赤外線放射は、放射源から直線的に遠ざかり、ビーム経路内の物体によって反射または吸収されます。人間の目に透明でないほとんどの物体から、赤外線は部分的に反射し、部分的に吸収される。吸収されたエネルギーの一部は内部で反射され、一部は再び放射される。これは、ガラスや気体、薄い透明プラスチックフィルムなど、人間の目には透明な物体にも当てはまる。さらに、放射線の一部は物体を透過する。図3は、これらの過程を示している。これらの過程を総合して、私たちは物体や物質の放射率と呼んでいる。

図 2 黒体の放射特性

図 3 熱交換と放射
可視光線と同様、表面が研磨されているほど、反射するエネルギーは大きくなる。したがって、表面の仕上げは発光係数にも影響する。温度を測定する場合、これは赤外線を透過せず、発光係数が低い物体にとって特に重要です。研磨されたステンレス鋼でできた物体は、粗い表面を持つ同じ物体よりも放出係数が著しく低い。機械加工の後、例えば旋盤加工の後、粗い物体には多くの小さな溝や凹凸があり、加工物の反射率を著しく低下させる。
エネルギー保存の法則は、透過、反射、放出(吸収)される赤外線エネルギーの係数の和は1に等しくなければならないと定めている。
σλ + αλ + τλ = 1
さらに、放出係数は吸収係数に等しい:
ελ = αλ
以下を適用:
ελ = 1 - σλ+ τλ
エネルギー保存の法則は、透過、反射、放出(吸収)される赤外線エネルギーの係数の和は1に等しくなければならないと定めている。
σλ + αλ + τλ = 1
さらに、放出係数は吸収係数に等しい:
ελ = αλ
以下を適用:
ελ = 1 - σλ+ τλ

図 4 黒体、灰色体、および多色放射体の比較
この係数は、波長に対する表面の特性を表す変数として、プランクの方程式で使用することができる。
ελ = 1 - σλ
赤外線を反射も透過もしない物体は黒体と呼ばれる。自然の黒体は知られていない。理論上、また他の物体の計算上、黒体の放射係数は1.0である。実際には、小さな円筒形の入口開口部を持つ赤外線不透過性の球体を使用することで、真の黒体の最良の近似が得られる。このような物体の内面は、0.998の放出係数を持つ。
放出係数は、同じ温度の灰色体と黒体から放出される熱放射の比率を示す尺度である。灰色体とは、すべての波長で同じ放射率を持ち、黒色体よりも赤外線の放射が少ない物体である。バンド放射体とは、例えば金属などのように、波長によって放射率が変化する物体である。
ελ = 1 - σλ
赤外線を反射も透過もしない物体は黒体と呼ばれる。自然の黒体は知られていない。理論上、また他の物体の計算上、黒体の放射係数は1.0である。実際には、小さな円筒形の入口開口部を持つ赤外線不透過性の球体を使用することで、真の黒体の最良の近似が得られる。このような物体の内面は、0.998の放出係数を持つ。
放出係数は、同じ温度の灰色体と黒体から放出される熱放射の比率を示す尺度である。灰色体とは、すべての波長で同じ放射率を持ち、黒色体よりも赤外線の放射が少ない物体である。バンド放射体とは、例えば金属などのように、波長によって放射率が変化する物体である。
また、素材によって発光係数が異なるため、ある温度で異なる強度の赤外線を放射する。これは、塗料の材質が対象物の材質と明らかに異なる場合を除き、一般に色の関数ではない。これが当てはまる例として、アルミニウム粒子を多量に含む金属効果塗料がある。ほとんどの塗料は、色調に関係なく同じ放出係数を持つ。一方、アルミニウムの発光係数は大きく異なり、その結果、金属効果塗料の発光係数は異なる。
物体の組成と表面構造に加えて、第三の要因が発光係数に間接的な影響を与える:センサーのスペクトル範囲。これは対象物には直接影響しないが、センサーが対象物から放射されるスペクトルをどのように認識するかに影響する。
ガラス、プラスチック、シリコンなどの部分的に透明な材料は、対応する選択フィルターと組み合わせて、ある範囲で測定することができる。
物体の組成と表面構造に加えて、第三の要因が発光係数に間接的な影響を与える:センサーのスペクトル範囲。これは対象物には直接影響しないが、センサーが対象物から放射されるスペクトルをどのように認識するかに影響する。
ガラス、プラスチック、シリコンなどの部分的に透明な材料は、対応する選択フィルターと組み合わせて、ある範囲で測定することができる。

図 5 波長に依存するさまざまな材料の放射係数
赤外線温度測定において、発光係数が特に重要なパラメータであることは、これまでの段落から明らかである。被測定物の放射率を正確に知り、測定に考慮しない限り、得られた測定値が正確である可能性は極めて低い。放射率を決定するには、基本的に2つの方法があります。表から求める方法と、比較測定によって求める方法である。しかし、表のデータは一般的に理想化された実験室条件下で決定されているため、特に低係数の場合に大きな偏差を引き起こす環境の影響は考慮されていない。また、この表は、基礎となる測定温度と測定波長を特定していない。第一近似値として、表の値は確かに非常に有用である。比較測定では、測定対象物を熱電対やその他の温度センサーで測定し、同じ温度を表示するように赤外線温度計の発光係数を設定します。経験則として、ほとんどの不透明な非金属材料の発光係数は0.85~0.95と高く、比較的安定している。ほとんどの酸化していない金属材料の場合、発光係数は0.2~0.5の範囲にあるが、金、銀、アルミニウムは例外で、発光係数はさらに低い。そのため、これらの金属の温度を赤外線温度計で測定することは困難である。周囲放射の反射成分が物体放射と同じ桁かそれ以上であるためである。
ほとんどの場合、材料の発光係数を決定することは可能であるが、材料が一定の発光係数を持たず、温度によって変化する場合には問題が生じる。これはほとんどの金属に当てはまりますが、シリコンや高純度の単結晶セラミックなど、他の材料にも当てはまります。
温度測定の基礎となる方程式と公式は、以前から知られ、証明されている。赤外線温度計を使用する日常業務で、ユーザーがこれらの公式を使用する必要はほとんどないだろう。しかし、これらの基本を知ることで、特定の変数やパラメータが互いにどのような影響を及ぼすかをよりよく理解することができる。
1.キルヒホッフの放射則
ある温度Tと波長lにおいて、放射率eは吸収率に等しい
e = α
このことから、実際の物体の放射束øλは、同じ温度における黒体øsに物体の放射率を乗じたものに等しい
øλ = ε * øs
2.ステファン・ボルツマンの法則
物体の温度Tが大きいほど、ある放射率εと放射面A(k = 定数)に対してより多くの放射パワーPが放射される
P =k*ε*A*T4
3.ウィーンの変位則
エネルギー放射の最大値が位置する波長は、温度の上昇とともに短波長側にシフトする。
λmax = 2.89 * 103 μmK/T
4.プランクの方程式
この方程式は、波長、温度T、放射パワーの関係を記述している
ほとんどの場合、材料の発光係数を決定することは可能であるが、材料が一定の発光係数を持たず、温度によって変化する場合には問題が生じる。これはほとんどの金属に当てはまりますが、シリコンや高純度の単結晶セラミックなど、他の材料にも当てはまります。
温度測定の基礎となる方程式と公式は、以前から知られ、証明されている。赤外線温度計を使用する日常業務で、ユーザーがこれらの公式を使用する必要はほとんどないだろう。しかし、これらの基本を知ることで、特定の変数やパラメータが互いにどのような影響を及ぼすかをよりよく理解することができる。
1.キルヒホッフの放射則
ある温度Tと波長lにおいて、放射率eは吸収率に等しい
e = α
このことから、実際の物体の放射束øλは、同じ温度における黒体øsに物体の放射率を乗じたものに等しい
øλ = ε * øs
2.ステファン・ボルツマンの法則
物体の温度Tが大きいほど、ある放射率εと放射面A(k = 定数)に対してより多くの放射パワーPが放射される
P =k*ε*A*T4
3.ウィーンの変位則
エネルギー放射の最大値が位置する波長は、温度の上昇とともに短波長側にシフトする。
λmax = 2.89 * 103 μmK/T
4.プランクの方程式
この方程式は、波長、温度T、放射パワーの関係を記述している

赤外線温度計の構想
1.物体から放射されるエネルギーを集束させるレンズ
2.放射エネルギーを電気信号に変換する検出器
3.温度計を測定対象物の特性に適合させるための放射係数の調整
4.温度計の温度が出力信号に含まれるのを防ぐ周囲温度補償 長年にわたり、市販されている赤外線温度計のほとんどはこのコンセプトに従っている。温度計の温度が出力信号に含まれないようにする周囲温度補正。
長年にわたり、市販されているほとんどの赤外線温度計はこのコンセプトに従っていた。これらは用途が限定されており、今にして思えば満足のいく測定結果は得られなかった。しかし、当時の基準からすれば、完全に適切であり、非常に堅牢であった。

図 6 IR 温度計のブロック図
現代の赤外線温度計はこの基本コンセプトに基づいているが、時代とともに大幅に改良されている。最も重要な違いは、さまざまなタイプの検出器の使用、赤外線信号の選択的フィルタリング、検出器信号の線形化と増幅、4-20 mAまたは0-10 V DCなどの標準化された温度出力信号である。図6は、最新の赤外線高温計のブロック図である。
赤外線温度測定における最も重要な進歩は、赤外線の選択フィルタの導入によって達成された。これにより、より感度の高い検出器と、より安定した信号増幅器を使用できるようになりました。初期の赤外線温度計は、使用可能な検出器出力信号を得るために広い赤外線スペクトルに依存していたが、現代の検出器では1μm以上の帯域幅で完全に十分である。スペクトルを狭め、特定の波長を選択する必要性は、炭素や水素を含むために温度が測定に含まれるべきではない媒体を介して測定を行わなければならないことが多いという事実から生じる。さらに、IRスペクトルの広い範囲にわたって透過性のある物体や気体の温度を測定する必要がある場合もある。
- 8 - 14 μm: より遠距離の空気湿度の影響も排除されます。
- 7.9 μm: 広い範囲で赤外線を透過する薄いプラスチックフィルムの測定が可能です。
- 3.86 μm: 炎や燃焼排ガス中のCO2や水蒸気との干渉が効果的に抑制されます。
赤外線温度測定における最も重要な進歩は、赤外線の選択フィルタの導入によって達成された。これにより、より感度の高い検出器と、より安定した信号増幅器を使用できるようになりました。初期の赤外線温度計は、使用可能な検出器出力信号を得るために広い赤外線スペクトルに依存していたが、現代の検出器では1μm以上の帯域幅で完全に十分である。スペクトルを狭め、特定の波長を選択する必要性は、炭素や水素を含むために温度が測定に含まれるべきではない媒体を介して測定を行わなければならないことが多いという事実から生じる。さらに、IRスペクトルの広い範囲にわたって透過性のある物体や気体の温度を測定する必要がある場合もある。
- 8 - 14 μm: より遠距離の空気湿度の影響も排除されます。
- 7.9 μm: 広い範囲で赤外線を透過する薄いプラスチックフィルムの測定が可能です。
- 3.86 μm: 炎や燃焼排ガス中のCO2や水蒸気との干渉が効果的に抑制されます。
温度範囲は、測定に最適な波長を選択する上で重要な役割を果たす。プランクの方程式は、黒体について図2に示すように、温度が上昇するにつれて放射曲線の最大値が短波長側にシフトすることを示している。スペクトル範囲の選択的な選択が必要とされない用途であっても、スペクトル範囲をできるだけ短波長の狭い部分に限定することが有利になることがある。一つの利点は、多くの物体の有効発光係数が、波長の短い金属で最も高いことである。さらに、図7に見られるように、スペクトル範囲が狭いセンサーは、測定対象物の発光係数の変化の影響を受けにくいため、この制限は精度に有利な影響を与えます。

図 7 さまざまな波長における誤って設定された放射率の依存性
建設的なデザイン
赤外線温度計は、光学系、電子回路、技術、サイズ、筐体などが異なるさまざまな構成で製造されている。しかし、共通しているのは、赤外線信号から始まり、電子出力信号で終わる信号処理チェーンである。この一般的な測定チェーンは、レンズや光ファイバー、フィルター、検出器から構成される光学系から始まります。
アプリケーションの観点からは、視野は光学系の本質的な特性です。つまり、ある距離で測定スポットがどれだけ大きいかということです。測定距離と測定スポットの直径の比は距離比で表されます。実際には、固定焦点距離の高温計と焦点調節可能な光学系の高温計を選択することができます。固定光学系を持つデバイスは、焦点位置の物体にのみ焦点を合わせます。他の測定距離では、測定スポット径は計算された距離比に比例して大きくなります。このような光学系は主に大きな対象物に適しています。小さな対象物や測定距離が長い場合は、焦点調節可能な光学部品の使用をお勧めします。
測定スポット径を指定し比較する場合、その指定が放射パワーの何%を指しているかを知ることが重要です。例えば、エネルギーの98%に基づく測定スポットは、パワーの90%に基づく直径の2倍の大きさになります。これは、特に高温計の測定スポットと同じ大きさの小さなターゲットでは、かなりの測定誤差につながる可能性がある。
光学系のもう一つの側面は、ターゲットの照準である。照準補助のない装置では、レンズは表面に固定され、表面温度を測定する。これは特に、十分に大きな対象物に合わせられ、精密な測定が要求されない定置型センサーに適用される。より小さな対象物や、より遠距離で測定する機器には、レンズを通して見る光学部品、光スポット、レーザービームなどの形の照準器が不可欠である。
パイロメーターの感度は、多くの異なる検出器とフィルターの使用によって決定される。図8に見られるように、硫化鉛検出器は最も感度が高く、サーモパイルは最も感度が低い。ほとんどの検出器は、光電原理(赤外放射が入射すると電圧信号が発生する)または光伝導(赤外放射が入射すると抵抗値が変化する)に基づいて動作する。
放射エネルギーが低いため、低温ではそれに対応する広帯域のスペクトルが必要となり、したがって測定波長も長くなる。高温では、狭帯域フィルターによって感度が大幅に低下する。これにより、波長依存の干渉を最小限に抑えることができる。
アプリケーションの観点からは、視野は光学系の本質的な特性です。つまり、ある距離で測定スポットがどれだけ大きいかということです。測定距離と測定スポットの直径の比は距離比で表されます。実際には、固定焦点距離の高温計と焦点調節可能な光学系の高温計を選択することができます。固定光学系を持つデバイスは、焦点位置の物体にのみ焦点を合わせます。他の測定距離では、測定スポット径は計算された距離比に比例して大きくなります。このような光学系は主に大きな対象物に適しています。小さな対象物や測定距離が長い場合は、焦点調節可能な光学部品の使用をお勧めします。
測定スポット径を指定し比較する場合、その指定が放射パワーの何%を指しているかを知ることが重要です。例えば、エネルギーの98%に基づく測定スポットは、パワーの90%に基づく直径の2倍の大きさになります。これは、特に高温計の測定スポットと同じ大きさの小さなターゲットでは、かなりの測定誤差につながる可能性がある。
光学系のもう一つの側面は、ターゲットの照準である。照準補助のない装置では、レンズは表面に固定され、表面温度を測定する。これは特に、十分に大きな対象物に合わせられ、精密な測定が要求されない定置型センサーに適用される。より小さな対象物や、より遠距離で測定する機器には、レンズを通して見る光学部品、光スポット、レーザービームなどの形の照準器が不可欠である。
パイロメーターの感度は、多くの異なる検出器とフィルターの使用によって決定される。図8に見られるように、硫化鉛検出器は最も感度が高く、サーモパイルは最も感度が低い。ほとんどの検出器は、光電原理(赤外放射が入射すると電圧信号が発生する)または光伝導(赤外放射が入射すると抵抗値が変化する)に基づいて動作する。
放射エネルギーが低いため、低温ではそれに対応する広帯域のスペクトルが必要となり、したがって測定波長も長くなる。高温では、狭帯域フィルターによって感度が大幅に低下する。これにより、波長依存の干渉を最小限に抑えることができる。
赤外線センサーシステムの応答挙動を最適化するには、検出器のスペクトル曲線とその特性を考慮する必要があります。
赤外線温度計の電子回路は、最終的にリニアな電流0(4)~20mAまたは電圧信号0(2)~10Vを生成するために、検出器の出力信号を線形化します。リニアライゼーションは、現在ではマイクロプロセッサーを使用したソフトウェアで行われることが多い。
これにより、アナログのリニアライゼーションと比較して、より大きな測定スパンでより高い精度を達成することができる。
信号をデジタル化してインターフェースに出力したり、コントローラー、インジケーター、レコーダーに供給することもできる。構成にもよりますが、赤外線温度計には、アラーム、間欠測定用の調整可能な最小/最大メモリ、調整可能な測定間隔と応答時間、サンプルホールド機能などの追加機能があります。
冒頭で述べたように、非接触温度測定の利点は、応答時間が短いことです。低温デバイス用の熱電ディテクターは30msの応答時間を実現しています。光電式高温ディテクターの応答時間は2msです。
高速応答時間のセンサーをアプリケーションで使用する場合、制御ループの他のコンポーネントも、対応する処理や作動速度を可能にする必要があります。
赤外線温度計の電子回路は、最終的にリニアな電流0(4)~20mAまたは電圧信号0(2)~10Vを生成するために、検出器の出力信号を線形化します。リニアライゼーションは、現在ではマイクロプロセッサーを使用したソフトウェアで行われることが多い。
これにより、アナログのリニアライゼーションと比較して、より大きな測定スパンでより高い精度を達成することができる。
信号をデジタル化してインターフェースに出力したり、コントローラー、インジケーター、レコーダーに供給することもできる。構成にもよりますが、赤外線温度計には、アラーム、間欠測定用の調整可能な最小/最大メモリ、調整可能な測定間隔と応答時間、サンプルホールド機能などの追加機能があります。
冒頭で述べたように、非接触温度測定の利点は、応答時間が短いことです。低温デバイス用の熱電ディテクターは30msの応答時間を実現しています。光電式高温ディテクターの応答時間は2msです。
高速応答時間のセンサーをアプリケーションで使用する場合、制御ループの他のコンポーネントも、対応する処理や作動速度を可能にする必要があります。

図 8 さまざまなセンサーのスペクトル曲線
単色測定:1波長での温度測定
単波長温度測定は、ある波長の表面から放射されるエネルギーを測定する。シンプルな外部ディスプレイを備えたポータブル・プローブから、対象物に焦点を合わせた覗き窓に温度を表示する高度なポータブル機器まで、さまざまな設計の機器がある。メモリー機能やプリント機能もある。定置型オンラインセンサーは、外部エレクトロニクスを備えたシンプルな小型検出器から、PIDコントローラーを内蔵した堅牢で複雑なアセンブリーまで幅広い。 ファイバーオプティクス、シースルーオプティクス、レーザー照準装置、水冷、スキャナーシステムなどは、プロセスのモニタリングや制御に使用されるオプションです。最近では、ビデオカメラを内蔵した高温計も提供されており、測定に加えて、制御室から測定ポイントを光学的に制御することも可能です。サイズ、性能、堅牢性、柔軟性、信号処理の面で大きな違いがあります。
アプリケーションを計画・設計する場合、センサーの構成、フィルター、温度範囲、光学系、応答時間、エミッションファクターは、詳細に考慮しなければならない重要な基準です。
赤外線スペクトル範囲と温度範囲の選択は、常に特定のアプリケーションと併せて考慮しなければなりません。図2に示すスペクトル曲線から、高温には短波長が適しており、低温は長波長域で測定すべきであることがわかる。ガラスやプラスチックフィルムのような透明な物体を測定する場合は、狭帯域の選択フィルターが必要である。例えば、ポリスチレンフィルムのCH吸収範囲は3.43μmであり、その時点では赤外線を透過しない。同様に、多くのガラス状材料は5μm付近で不透明になる。逆に、2μmまでの範囲のフィルターを持つセンサーは、例えば真空や圧力チャンバー用のガラス窓を通した測定を可能にする。また、測定ポイントが限られたチャンバーや周囲温度が高いチャンバーでの測定には、光ファイバーケーブルを使用する方法もある。
単一波長を使用したIR温度測定は、それゆえ汎用性が高く、かつシンプルな技術であり、製品温度の制御が安定した製品品質のために不可欠な多くの用途に十分対応できる。
アプリケーションを計画・設計する場合、センサーの構成、フィルター、温度範囲、光学系、応答時間、エミッションファクターは、詳細に考慮しなければならない重要な基準です。
赤外線スペクトル範囲と温度範囲の選択は、常に特定のアプリケーションと併せて考慮しなければなりません。図2に示すスペクトル曲線から、高温には短波長が適しており、低温は長波長域で測定すべきであることがわかる。ガラスやプラスチックフィルムのような透明な物体を測定する場合は、狭帯域の選択フィルターが必要である。例えば、ポリスチレンフィルムのCH吸収範囲は3.43μmであり、その時点では赤外線を透過しない。同様に、多くのガラス状材料は5μm付近で不透明になる。逆に、2μmまでの範囲のフィルターを持つセンサーは、例えば真空や圧力チャンバー用のガラス窓を通した測定を可能にする。また、測定ポイントが限られたチャンバーや周囲温度が高いチャンバーでの測定には、光ファイバーケーブルを使用する方法もある。
単一波長を使用したIR温度測定は、それゆえ汎用性が高く、かつシンプルな技術であり、製品温度の制御が安定した製品品質のために不可欠な多くの用途に十分対応できる。
レシオ測定:2波長以上の温度測定
赤外線温度計による正確な温度測定において、発光係数が重要な役割を果たすこと、あるいはビーム経路に中間媒体が存在することを考えれば、研究者がこれらの干渉に左右されずに温度を測定できるセンサーの開発に取り組んでいることは驚くべきことではない。これに対する一般的で実績のあるアプローチは、比率測定またはマルチカラー測定である。この方法では、1つの波長におけるエネルギーの絶対量ではなく、2つの異なる波長におけるエネルギーの比率を測定する。マルチカラー測定」という言葉は、可視色と温度を組み合わせるという古い考え方に由来している。
このコンセプトの有効性は、測定対象物の表面特性の変化や、測定対象物に対する視錐台に位置する障害物が、両方の検出器によって同じように知覚されるという事実に基づいています。そのため、センサー出力信号間の比率は変わらず、測定温度も変わりません。図9は、この原理に従って動作する高温計の簡略図を示している。
このコンセプトの有効性は、測定対象物の表面特性の変化や、測定対象物に対する視錐台に位置する障害物が、両方の検出器によって同じように知覚されるという事実に基づいています。そのため、センサー出力信号間の比率は変わらず、測定温度も変わりません。図9は、この原理に従って動作する高温計の簡略図を示している。

図 9 比率測定
絶対値ではなく比率を測定することで、上述の条件下で、未知または変化する発光係数に起因する不正確さを回避することができる。
物体とセンサーの間の媒体が特定の波長を選択的に減衰させない限り、比率は一定に保たれ、したがって温度計で測定される温度も一定に保たれる。
したがって、この方法は、他の測定技術では解決が難しいか不可能な用途、例えば、セメントキルン内の温度測定や、金属の真空溶解のようにプロセス中に曇る窓を通した測定に適している。
もちろん、この方法には考慮しなければならない限界もある。レシオ測定は、アルミニウムのような着色発光体には適さない。同様に、透過率が変化する窓や高温のパイレックスを通した測定には使えない。さらに、この方法では、バックグラウンド温度が測定対象物の温度より高い場合、その温度が記録され測定される傾向がある。
物体とセンサーの間の媒体が特定の波長を選択的に減衰させない限り、比率は一定に保たれ、したがって温度計で測定される温度も一定に保たれる。
したがって、この方法は、他の測定技術では解決が難しいか不可能な用途、例えば、セメントキルン内の温度測定や、金属の真空溶解のようにプロセス中に曇る窓を通した測定に適している。
もちろん、この方法には考慮しなければならない限界もある。レシオ測定は、アルミニウムのような着色発光体には適さない。同様に、透過率が変化する窓や高温のパイレックスを通した測定には使えない。さらに、この方法では、バックグラウンド温度が測定対象物の温度より高い場合、その温度が記録され測定される傾向がある。
図10は、温度によって放出係数が変化する様々な製品の例を示している。例えば、黒鉛は、高い一定の放出係数を持つものと思われがちである。
発光係数が波長によって変化する有色発光体については、全波長のエネルギーを測定するマルチカラー温度計がある。このような用途に使用するには、当該製品の表面特性を詳細に分析する必要がある。発光係数、温度、波長、表面化学の関係を分析しなければならない。このデータは、異なる波長での発光を意味のある方法で温度に関連付けるアルゴリズムを設定するために使用することができる。
測定に使用される波長の1つに対応する粒子径を持つ媒体が視野内にある場合、比率も歪む。
これらの制限にもかかわらず、比率測定は多くの用途で非常にうまく機能する。アプリケーションによっては、この方法が温度測定のための唯一の賢明な解決策ではないにしても、最良の方法となる。
発光係数が波長によって変化する有色発光体については、全波長のエネルギーを測定するマルチカラー温度計がある。このような用途に使用するには、当該製品の表面特性を詳細に分析する必要がある。発光係数、温度、波長、表面化学の関係を分析しなければならない。このデータは、異なる波長での発光を意味のある方法で温度に関連付けるアルゴリズムを設定するために使用することができる。
測定に使用される波長の1つに対応する粒子径を持つ媒体が視野内にある場合、比率も歪む。
これらの制限にもかかわらず、比率測定は多くの用途で非常にうまく機能する。アプリケーションによっては、この方法が温度測定のための唯一の賢明な解決策ではないにしても、最良の方法となる。

図 10 多くの材料では、排出係数は温度によって変化します。この図は、いくつかの一般的な材料を示しています。
概要
図11は、アプリケーションの本質的な要素を改めて示している。ここで最も重要なのは、測定対象物の表面である。
さらに、最適な測定器を選択する際には、炎の存在、赤外線放射ヒーター、誘導炉、大気の性質(ほこり、汚染された窓、煙、熱など)など、周囲の条件も考慮する必要があります。
さらに、最適な測定器を選択する際には、炎の存在、赤外線放射ヒーター、誘導炉、大気の性質(ほこり、汚染された窓、煙、熱など)など、周囲の条件も考慮する必要があります。

図 11 妨害要因
赤外線温度計測は成熟した技術であり、常に最適化され、新しいアプリケーションに適応しています。研究分野だけでなく、幅広い産業分野でその価値が日々証明されています。基礎となる技術が正しく理解され、関連するすべてのアプリケーションパラメータが考慮されていれば、この測定方法は、装置が慎重に設置されている限り、一般的に望ましい結果をもたらします。
したがって、温度計メーカーを選択する際の1つの基準は、保護および設置用アクセサリーの有無である。また、これらの付属品によってセンサーを素早く取り外し、必要に応じて交換できるかどうかも考慮する必要があります。これらのガイドラインが守られていれば、最新の赤外線温度計は熱電対やPt100センサーよりも確実に動作することが多い。
したがって、温度計メーカーを選択する際の1つの基準は、保護および設置用アクセサリーの有無である。また、これらの付属品によってセンサーを素早く取り外し、必要に応じて交換できるかどうかも考慮する必要があります。これらのガイドラインが守られていれば、最新の赤外線温度計は熱電対やPt100センサーよりも確実に動作することが多い。